2026年02月20日

2023年02月23日

撮影:田邊アツシ 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]
アートとケアの観点からテクノロジーをとらえなおし、アートとケアとテクノロジーの可能性をひろげるプロジェクト「Art for Well-being」。
文化庁「令和4年度 障害者等による文化芸術活動推進事業」
このプロジェクトでは、病気や事故、加齢、障害の重度化など、心身がどのような状態に変化しても、さまざまな道具や技法などのテクノロジーとともに、自由に創作をはじめることや、表現することを継続できる方法を考えます。
<たんぽぽの家>が2020年から試行的に始めてきたこのプロジェクトは、2022年から文化庁の一事業としても取り組み、先進的な実践や考え方を調査して発信しています。
今回インタビューしたのは、<山口情報芸術センター・通称「YCAM(ワイカム)」>の社会連携担当の菅沼聖 ( すがぬま・きよし )さんと、R&Dディレクター伊藤隆之 ( いとう・たかゆき )さん。
YCAM(ワイカム)は、山口県山口市にあるアートセンターです。
展示空間のほか、映画館、図書館、ワークショップ・スペース、レストランなどを併設しています。
2003年11月1日の開館以来、メディア・テクノロジーを用いた新しい表現の探求を軸に活動しており、展覧会や公演、映画上映、子ども向けのワークショップなど、多彩なイベントを開催しています。

地方都市にありながら、最先端のメディア・テクノロジーを活用した事業を展開し、世界から注目を集める施設。
でも、この説明を聞いただけだと、アートセンター? メディア・テクノロジー? 一体どんなことをやっているのと思う方も多いかもしれません。
実際、「地域の人たちはYCAMをどう捉えているの?」という質問に、菅沼さんは「捉えどころのない施設だと思います。美術館でも、科学博物館でもないアートセンターという名称もそうですし。やっている事業も、実験的、領域横断的なものが多く、固定されたイメージがつきにくいのかもしれません。もちろん個々の事業に対してのファンはいます。例えば、シネマ事業に毎回参加される人、テクノロジーとスポーツを融合させた運動会事業に毎回される人、みたいに。メタ的にYCAMの活動を理解してもらうのはなかなか難しいので、 “進化するアートセンターです”と伝える時もあります。」と言います。
捉えどころがないというのは、それだけ多様な顔を持っているということでもあります。
そこで今回は、YCAMの活動の中でも、特に「障害や福祉」に関わるもの、まさに、アートとケアとテクノロジーの可能性をひろげるようなものをご紹介いただきながら、その背景にある考え方や、地方の公的施設がそういった事業に取り組む意義などについて伺いました。
目次
菅沼:
最初に、今回のテーマである「障害や福祉」に関わる活動をざっと紹介します。
■「パーソナルスペース再発見」2017年
このプロジェクトは准教授東京大学先端科学技術研究センター准教授・小児科医であり当事者研究が専門の熊谷晋一郎さん、振付家・ダンサーの砂連尾理さんなど、コラボレーターがいることで実現しました。「人によって違う快適な人との距離。他の人はどのようなパーソナルスペースでコミュニケーションをとっているのか?」といった疑問をもとに、「さまざまなパーソナルスペースを体験することで見えてくるコミュニケーションの可能性を探す」ワークショップです。
https://www.ycam.jp/events/2017/rediscovering-personal-space/

■「みらいのしごと after 50」2022年
KOEL DESIGN STUDIO by NTT Communicationsとの共催で実施した、2日間の共創ワークショップ。テーマは、「みらいのしごとAfter 50 〜50代以降の働き方、生き方を、地域で創造的に暮らす高齢者に学び、構想する〜」。ワークショップの中では、中山間地域の働き方のビジョンを、地元の人に聞いてみるフィールドワークなどを行いました。
■「ビデオ・プリゼント」2022年
厚生労働省の補助金を用いて、障害のある人(主に自閉症)とその保護者や支援者へ、映像制作の技術を手渡すプログラムです。映像制作をとおしたコミュニケーションを、ワークショップ化して提供しました。これは、中国・四国Artbrut Support Center passerelle(パスレル)さんと一緒に実施しました。
また、その成果物である参加者が制作した12本の短編映像作品を特設ウェブサイトで公開しています。
■「触覚伝話 」2021年
NTTコミュニケーション科学基礎研究所が企画制作、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 KMD Embodied Media Project、名古屋工業大学、YCAMが制作協力で作りました。
触覚を簡単に転送できる装置です。オンライン会議システムであるzoomとも併用できます。コロナ禍でやっていたので、こういう課題設定になっています。人と人が気軽に会えない、触れ合えないといった社会において触覚コミュニケーションの可能性を探索しました。
ここで、実際に使っている様子の動画をご覧いただけます。
■「The EyeWriter 2.0」 2011年
「The EyeWriter」はALS(筋萎縮性側索硬化症)で体が麻痺したアメリカのグラフィティアーティストTempt1が「再び絵を描けるように」という願いをきっかけに、2010年に始まったプロジェクトです。アーティストやエンジニアをはじめ、世界各地の多くの参加者によって、オープンソースソフトウェアと手軽なデバイスによる、目の動きだけで絵を描く装置が開発されました。
YCAM では、LabACT(ラボ・アクト)というプロジェクトの一環として、2011年10月に公開された展覧会LabActVol1 The EyeWriterに際し、The Eyewriterの日本語制作マニュアル「EyeWriter 2.0 のつくりかた」を作りました。その後、地域の障害者施設で働く職員さんから連絡がきたりと、アート業界以外の反響が多くありました。

菅沼:
こういう感じでやってはいますが、YCAM自体は、アート制作を主軸にしていますので、YCAM側から障害、福祉というテーマを持ち出すというよりは、コラボレーターによって、技術やアイデアをどう応用していけるのかということを試みているという感じです。近年はこうした流れをクリエイションサイクルに取り入れることに挑戦しています。2020年からYCAMの中に社会実装を推進するチームを作りまして、メディアアートの研究開発から出た知見を二次応用、三次応用していく編成を作っています。そこでは、YCAMがプレイヤーになるのではなく、<外のプレイヤー、意図を持っている人とつながり、プロジェクトが立ち上がる>ことに取り組んでいる。YCAMはあくまでプラットフォームなので、他の組織と結びついて、知見を還元していくかたちをとっているんですね。そうすると、福祉とか障害とか多様なテーマと関係を持つことができて、YCAMとしては面白い状況をつくれるのかなと。
― 森下:発信した時に、地域や全国の公共施設、メディアやテクノロジーの専門家からの反応を感じることはありますか?
伊藤:
ものによりますね。「EyeWriter2.0」はとても大きな反響がありました。当時は視線解析のハードウェアは70〜80万円と高価だったんですね。でもこのマニュアルを見て自作すれば、1〜2万円くらいでできる。それでたくさん問い合わせがきて。ただ、こちらも余裕がなく、あまりサポートというか、コラボレーションができなかったのですが。
もちろん、もともとの「Eye Writer」というプロジェクトが、世界的な評価が高かったのも、反響が大きかった理由の1つだと思います。
菅沼:
「パーソナルスペース再発見」は、YCAMにとって発見が多かった。また、外部でプレゼンすると興味を持ってもらえることが多いプロジェクトです。
― 森下:「パーソナルスペース再発見」につながるプロジェクトで、熊谷晋一郎さんにお声がけした経緯について聞かせてください。
伊藤:YCAMスタッフが、熊谷さんの本を読んで、熊谷さんのやっていることに興味を持っていて。砂連尾理さんと東京工業大学リベラルアーツセンター准教授の伊藤亜紗さんが間に入ってくれて、話をしていくうちに、熊谷さんともつながって、こういうプロジェクトになっていったんです。
プロジェクトの位置付けとしては、テクノロジーを通じてダンスを生み出すYCAMの研究開発プロジェクト「Reactor for Awareness in Motion(RAM=ラム)」を発展させた新しいプロジェクト「Perception Engineering(パーセプション・エンジニアリング)」というものです。 そのキックオフイベントとして、、研究成果の一部を展示したり、ワークショップ「パーソナルスペース再発見」を行ったりしました。
― 大井:RAMでは、モーションキャプチャーシステム「MOTIONER」を開発されていました。それを使っていたら、パーソナルスペースみたいなところに広がっていくんじゃないかといった議論がYCAM内部であったんでしょうか?
伊藤:
RAMは「デジタルのテクノロジーを使って、どれだけ人の振る舞いをかえていけるか?」「身体を拡張していくということと、身体と環境の関わり、身体性に影響をもたらすことができるか?」がテーマでした。
それについて熊谷さんと話をしているうちに、熊谷さんから自閉症の人はパーソナルスペースが極端に狭い人が多いという話が出てきて。話しているうちに、パーソナルスペースを計測して可視化するアイデアにつながっていきました。
一概に自閉症と言っても、人によって様々ですし、視力が弱いとか、聴力が弱いとかといったことと関連があることもあるというお話だったので、買ってきたメガネにテープを貼って仮想の弱視状態をつくって人と会話をしてみたり。イヤーマフをつけてメガネをかけて、演劇の芝居のシーンをつくって、誰かと会話をするシーンをみんなで再現してみたり。そうすると、話しかける相手に、すごく近づかないとわからないし声も聞こえないんですよね。そうしたことを通して、距離感が自分とは異なる人の状態の一端を理解することを試してみたりなど、色々な実験を積み重ねた先に、ワークショップの中で「計測されたパーソナルスペースを床にプロジェクターで投影して、さらに人と交換してみる」っていうのをやってみたんですね。人のパーソナルスペースで対話してみる。そうするとやっぱり違和感があったり。学びがすごく多かったです。
― 森下:「パーソナルスペース再発見」はすごく面白そうでした。特に、その交換するというのがどんな感じなのかな、と思って。具体的にどういうテクノロジーでパーソナルスペースをビジュアライゼーションしたんでしょうか。
伊藤:
モーションキャプチャーシステムを簡単に使えるように工夫して、位置計測のためのマーカーを背中に背負えるようにして、それを背負った人の位置と向きが計測できるようにしました。そうして、その人の足元に扇型にパーソナルスペースを表示しました。
パーソナルスペースは、三人で対話するときの三者の間の位置関係から推測しました。まず適当に三人で何か話をしてもらって、モーションキャプチャーで各人の位置と向きは分かりますから、そのデータを使ってそれぞれのパーソナルスペースを推測し、その後表示しました。そのあとで、それを見ながら交換して会話してみたりしました。
最後は、パーソナルスペースの編集をやってみて。iPad上で、絵を描いたり、穴をあけたりもできるんです。さすがにそこまでいくと、「ちょっとちがうかな」と熊谷さんは言っていましたが(笑)。ただ、穴をあけたところに人が入ると意外と心地がよかったりして。こちらとしては何かありそうだ、という感触を得て終わりました。
― 森下:熊谷さんは、これに参加されて、論文を書いたりはされたのでしょうか。
伊藤:
論文化を試みたんですが、色々あって頓挫してしまって。実験のデータはたくさんとったんですが、なかなかうまくいかなかったです。
― 大井「Perception Engineering(パーセプション・エンジニアリング)」プロジェクトでは、他にも何か取り組んでいるのでしょうか
伊藤:
その時は2本だてで、もう一つはソニーコンピュータサイエンス研究所(ソニーCSL)の研究員・笠原俊一さんとの共同研究がありました。自分たちがそれまでに作っていたRAMというシステムのデモプログラムの中に、モーションキャプチャーを使って計測した体の動きを画面の中で実際よりもほんの少し未来を予測して表示するというものがあったんです。そこをずっと掘り下げて、VR空間でそういったことが行われたときに人は自分の身体の状態をどう感じるのかという研究でした。VR空間で自分の手だとかが、実際に動くよりも、ほんとに少しだけ早く動くんですよ。そうすると、体が軽く感じたりする。自分の身体の動きを時間的・空間的に変調させることで、身体の軽さや重さなど物理的な感覚の変化が生み出される。それは、ゲーム形式で体験できるインスタレーション「RADICAL BODIES―VRでダンス・ダンス(笠原俊一+YCAM)」を制作したり、論文化して発表したりもしました。
菅沼:
先ほども紹介しましたが、近年、YCAMでは社会連携事業として、メディアアート制作の知見をコラボレーターとともに社会応用することに注力しています。現在、教育やまちづくりなど多種多様なフィールドで展開しています。個人ベースで動いているものも多いです。例えば「ビデオ・プリゼント」はYCAMアーティスティック・ディレクターの会田大也さんが担当しています。
これは、2010年に行った、市民とビデオを撮って、映像祭をする「meet the artist(ミート・ジ・アーティスト)」の知見が大いに活かされています。
「meet the artist(ミート・ジ・アーティスト)」
https://www.ycam.jp/asset/pdf/press-release/2010/meet-the-artist.pdfhttps://www.ycam.jp/asset/pdf/press-release/2010/meet-the-artist.pdf
― 森下:「ビデオ・プリゼント」はウェブサイトで見ましたが、まさに、すでにある技術を、いろんな人が参加しやすくする、敷居を下げるものに思えました。
菅沼:
社会連携事業で重視しているのはYCAMの知見の「手渡し方」です。YCAMはプレイヤーにはなれないので、ツールやノウハウの水平展開を目指しているんです。
テクノロジーが持つ応用性の高さを活かし、受けて側の目的やモチベーションをサポートしていくのが、プラットフォームとしてのYCAMのあり方なのかなと思っています。YCAMに蓄積する知見は、アート表現や学びを中心とした研究開発から生まれます。企業や大学で行うような研究開発とは少し異なり、「美しさ」のようなものの探究は必ずしも合目的なプロセスを辿るとは限りません。だからこそ、アート制作から生まれたアイデアやツールには、他者によって介入する余白があるとも言えるのではないでしょうか。
― 森下:いままでの知見がストックとしてあって、それを水平展開する。
菅沼:
知見をストックしているのは人です。つまりYCAMでメディアアート制作に関わっているスタッフですね。人が核となり、そこにツールとメソッドがあると水平展開がうまくいくように思います。
個人的には、新たな価値創出(イノベーション)の中心にはアート制作に代表される、なんの制約も受けない実験的な行為があるべきと思っているんですね。そこに変な物差しが当てられると実験性が失われていくとも思っているんで。何かに役立てたいとか、人をこれだけ集めたいとかっていう目的や評価指標が入ってくれば入ってくるだけ、そっちに引っ張られてしまう。そこをなるべく切り離したいので、ツール化、メソッド化し、二次的、三次的に応用した先で社会で活かせるように、社会実装チームをしっかり運用していく。そういう体制づくりがデザインできると思っています。
アート事業にはなるべく費用対効果みたいなものをあてないということは、これからの、表現を生業とするような文化施設にとってはイシューになると自分は思っています。まだYCAMの社会実装チームは始まって2年くらいしか経っていないので、いま事例をいろいろ増やして、実証実験を繰り返している段階です。
伊藤:
とはいえ、アートか社会かという対立ではないと思っています。YCAMはそもそもアートをやる組織として市からお金をもらっているというのが基本にあります。かつ、そのアートも、いわゆる楽しいものを作りましたとかいうのではなくて。アート自体がもっている役割のいくつかとして、例えば社会的な問題を取り上げていくとか、人がうまく言葉とか文章にできなかった問題を示していくことで、観にきてくれたお客さんや、関わってくれた人たちに考えを促すというものがある。
それは、直接的に社会に関わる活動と比べて価値がないわけでは全然なくて、役割は違うけども両方とも大事だと僕は思っています。ただ、人数のキャパシティの限界、人件費の予算の限界はあって。そのなかで今までやってきたところを崩さずに、新しいことを模索していくっていう苦しいところにトライしている状況ではあります。
菅沼:
実験とか表現とか新しいことをする。ある種みんながリスクと感じるようなこととか、評価が見えないような文脈において、どのようにそれを社会的に、みんなが肯定しながら進められるのか。プロジェクトにしろ、組織にしろ、そういう枠組みを提案していかないと、萎縮していくばかりの世の中はいやなので。文化施設版として、その新しいモデルを作ろうとしているところなんです。
― 森下:来年2023年度でYCAMは開館20周年を迎えるとのこと。そもそも、20年前に、地方の自治体としてこういうものを作ろうということは、誰が提案したのでしょうか。
伊藤:
最初は、本当はコンベンションセンターを作る予定だったそうです。そのコンペで建築家の磯崎新さんがメディアセンターを作るべきという話をされたと聞いています。その話がコンペを通り、そこから施設を建てるまでのあいだに、ソフト研究会というものが立ち上がりました。その研究会には、磯崎さんのつながりで知識人やアーティスト、山口の人たちが入っていた。そこでどういう企画をしていくか、何年か話し合ったというのが始まりですね。
市の人たちも最初は、理解に困ったらしくて。何人かが有志で自費でオーストリアのArs Electronica(アルスエレクトロニカ)などに行ったりもされたと聞いています。国内のメディアアートのキュレーターとして有名な四方幸子さんや、YCAMのアーティスティック・ディレクターだった阿部一直さんらが行き先をコーディネートしたそうです。その中で、メディアアートが価値をもつかわからないが、少なくとも教育的効果は高い、と認識したことが骨格となっているような気がします。
また、開館当初はインパクトの強いメディアアートが中心でした。当時はYCAMも作品を作ることよりも見せることが重視されていたと思います。ただ、スタッフも作り手の人が多かったので、ここでは作れるぞ、という認識が2、3年目くらいから上がってきて。そこからだんだん、作品を作る場としてのラボを押していくようになってきたように思います。10周年の時には、リサーチや研究という話がどんどん出てきて。この10年で実際に文科省に研究機関登録もし、科研費も取れるようになりました。それにより、今日お話ししたようなコラボレーションも生まれています。
菅沼:
これからも新しいテクノロジーが次々と生まれ、社会の形が変化していく中で、私たちの生き方や考え方にも大きな影響が生じます。だからこそ、そういうことについて、前もって、応用性や倫理の問題も含めて考え、開かれた議論をしていくことは、企業や大学だけではなく、より市民生活に近い場所で公的なところもやるべきだと僕は思います。特に情報や市場が乏しい地方都市では、公がそういうことを担っていく行なっていくことには大きな意味があると思っています。
インタビュアー:
Good Job!センター香芝 森下静香
一般財団法人たんぽぽの家 小林大祐、大井卓也、岡部太郎
編集:井尻貴子

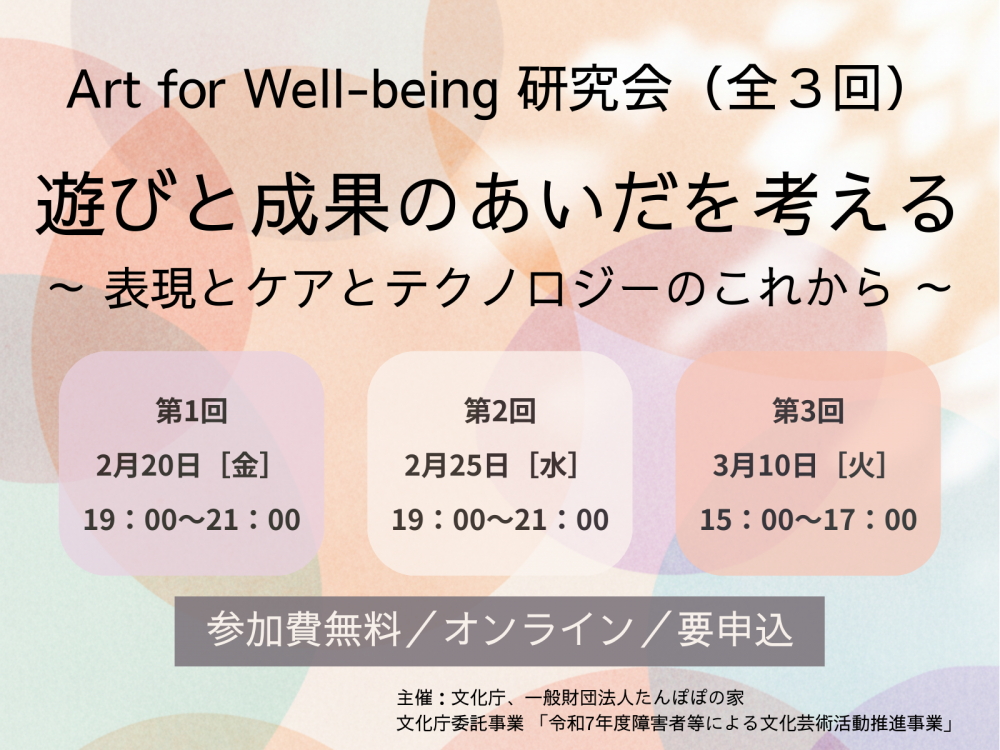
2026年01月26日

2026年01月26日




2026年01月26日