2026年01月26日


Art for Well-beingのアドバイザー、および展覧会の全体監修を務めていただいた小林茂さん(情報科学芸術大学院大学[IAMAS] 教授)より、令和4年度のプロジェクトを振り返るテキスト『Art for Well-beingからテクノロジーの哲学を考える』を寄稿いただきました。
目次
本事業「Art for Well-being」で取り組んできた成果を共有することを目的に開催した展覧会のサブタイトルは「表現とケアとテクノロジーのこれから」でした。このうち、「ケア」と「テクノロジー」あるいは「表現」と「ケア」の組み合わせについては、福祉施設の現場を思い浮かべると直感的に結びつくことでしょう。たとえば、福祉施設の日常において、障害のある人たちを支援するためのテクノロジーは、医薬品や支援機器など常に既に活用されています。また、絵画や詩などにより表現する、あるいは、音楽や演劇などを鑑賞することで表現に触れるといった活動が、とくに近年の福祉施設では推進されています。
しかしながら、ここで「表現」と「ケア」と「テクノロジー」の3つが並んでいることに違和感を覚えた方がいらっしゃるしれません。本事業で取り組んできた事例づくりにおけるテクノロジーとはAI、VR、触覚技術です。このように先端的なテクノロジーが福祉施設における「表現」や「ケア」で活用されている様子を想像することは難しいかもしれません。もしかしたら一部の方々は、先端的なテクノロジーを推進したい技術者や研究者が、障害のある人を対象にした実験を行おうとしたのではと訝しむかもしれません。
本事業では、現在進行形で起きているテクノロジーの変化に向き合うべく、メンバー=福祉施設を利用する障害のある人たち、スタッフ=ケアや表現活動の支援など施設側で関わる人たち、施設の外部から関わる技術者や研究者でチームを編成して進めてきました。これは、スタッフがメンバーを先端的なテクノロジーで支援するのでも、技術者や研究者がメンバーやスタッフに先端的なテクノロジーを提案するのでもありません。AIなどの先端的かつ大きな影響を与えうるテクノロジーについて、今後の方向付けに関わるべくチームで取り組んできました。これは一般的なモデルとは大きく異なるだけでなく、結構複雑なため説明が必要でしょう。本事業を振り返るにあたり、次のように進めていきます。これよりまず、私たち人間とテクノロジーの関係についていくつかの立場を紹介しつつ整理し、私の立場を示します。次にその立場より、本事業に取り組む中で見つけた可能性や課題を共有します。最後に、本事業からの学びを踏まえた展望について述べます。
テクノロジーについて議論する際にはいくつかの立場があります。もっとも一般的なのは、テクノロジーとは中立の単なる道具であるというものです。この立場では、テクノロジー自体には良いも悪いもなく、それを使う人によってすべてが決まると考えます。2023年2月に公開された映画『Winny』では、P2P(Peer to Peer)で匿名性を保ったままファイルを共有できるソフトウェア「Winny」をめぐる裁判が描かれました。このソフトウェアを開発した金子勇さん(1970-2013)は、技術者の表現としてWinnyをつくりました。このソフトウェアを用いて著作権侵害の蔓延という状況を生み出したのは、Winnyを使って著作権を侵害するファイルをやり取りした数多くの人々です。初審で有罪とされた金子さんと弁護団は最高裁まで争い、最終的には金子さんの無罪が確定しました。これは、テクノロジーそのものに善悪はなく、あくまでテクノロジーを使う側に責任があるという判断を示した重要な事件だとされています。一見すると、この考え方はもっとも妥当なものであるように思えます。私自身も、「Winny事件」と呼ばれるこの件に関して、金子さんを無罪とする判断を支持します。しかしながら、テクノロジーは中立の単なる道具であり、使う、使わない、どのように使うかはすべて人の自由であるかといえば、そうとも言い切れません。もしWinnyがなければ、あれだけ多くの人々が気軽に著作権侵害の蔓延に参加することはできなかったからです。
テクノロジーは中立の単なる道具であるとするのではなく、テクノロジーは自律的であり、人間を支配すると考える立場もあります。これは決定論的な見方とも言われます。最近大きな話題になっているテクノロジーに、大規模言語モデル(Large Language Models)があります。大規模言語モデルの1つ「GPT-4」は膨大なテキストの学習に基づいてテキストを生成できるモデルであり、このモデルを用いたチャットサービス「ChatGPT」が大きな話題になっています。ChatGPTをめぐり、これこそがAGI(Artificial General Intelligence:汎用人工知能)の始まりであり、これによって多くの人々の仕事が奪われる事態は避けられず、生き延びるためにはChatGPTを使いこなせるようになる必要があるのだと声高に叫ぶ人々が次々と現れています。また、イーロン・マスクのようにGPT-4を超える大規模言語モデルの開発を一時停止すべきだと主張した人々もいます。確かに、ChatGPTは驚くほど高性能に見えます。ChatGPTは、こちらが何を求めているかを適切に提示すれば、瞬時に回答を提示してくれ、こちらが納得するまで何度でも質問を繰り返すことができます。恐らく、実際にChatGPTを試した方の多くが、想像をはるかに超える解答が次々と生成される様子を目の当たりにして驚異——あるいは脅威——を感じたことでしょう。であれば、こうしたサービスが次々と登場し発展していく未来は不可避であると考え、テクノロジーを決定論的なものだとする立場も妥当であるように思われます。
もう1つ、テクノロジーは中立の単なる道具ではないとする立場を紹介しましょう。オランダの技術哲学者ピーター=ポール・フェルベークは、産科での超音波画像診断というテクノロジーに着目しました。超音波画像診断を用いれば、ダウン症などの可能性を高い精度で推測できます。確かに、このテクノロジーを利用するかしないかは個々の判断に任されています。しかしながら、利用した場合でも、利用しない場合でも、大きな影響を与えます。利用した場合、これから生まれてくる子どもに重い障害がある可能性が高いことが明らかになると、妊娠を人工的に中絶するのか、それとも先に進めるのかという重い判断が求められます。利用しなかった場合、障害や病気のある子どもを産むリスクを意図的に冒すことになります。フェルベークは、超音波画像診断というテクノロジーが胎児を潜在的な患者として構成し、妊娠という経験を医療プロセスや選択プロセスに変貌させてしまうと指摘しました。確かにこうした場合、テクノロジーは中立の単なる道具ではなく、利用の有無にかかわらず私たちに大きな影響を与えます。
ここまでで見てきたように、テクノロジーは中立の単なる道具だと言い切ることはできず、とくに先端的で今後の社会に大きな影響を与えると予想されるものに関しては不可避であるかのように思えますし、実際に大きな影響力を持つ場面も多々あります。本事業に取り組むにあたり私は、これら3つの立場を踏まえつつ、テクノロジーのうちとくに先端的なものに対して少し異なる立場で考えてきました。その立場とは、いっけん決定論的で不可避な変化をもたらすように思えるテクノロジーは実際のところ自在に解釈可能であり、初期段階における議論に多様な人々が参加することで方向付けることは可能であるというものです。
まず、自在に解釈可能であるという点についてみてみましょう。実際に福祉施設は、テクノロジーの自在な解釈に溢れています。福祉機器として認定され使用目的が明確に定められた高価な機器だけでは対応できない場面に対して、安価で手軽に入手できる製品を本来とは異なる目的のために利用している場面はありふれています。たとえば、百円均一ショップの製品を流用した自助具や、段ボールとテープで制作された道具がしばしば観察されます。そうしたことが可能なのは、ハイテク=先端的で複雑なテクノロジーに対して、ローテク=初歩的で単純なテクノロジーであるからだと思えるかもしれません。しかしながら、身の回りに溢れているプラスチック製品——たとえばストロー——だけをみても、設計、材料、加工、製造、流通など全体を視野に入れると極めて高度なテクノロジーの活用によりはじめて可能になっており、全体像をすべて把握している人が誰もいないほど複雑です。このように、ハイテクとローテクはまったく異なるものではなく、どの立場で見るかで区切りが変化する連続したものだと捉えるのが妥当でしょう。だとすれば、捉え方次第ではハイテクを身近なものだと考え、自在に解釈できるようになるのではないでしょうか。
次に、初期段階における議論の重要性についてみてみましょう。AIが社会に与える影響について研究するカナダのAspen Lillywhiteらは、学術論文、カナダの英字新聞記事、ツイートを対象として調査しました。その分析から、障害のある人に関するAIの議論はテクノロジー楽観主義的で、あくまで支援の対象者としてのみ位置付けられ、AIの発展が与える問題についてはほとんど扱われていないと指摘しました。往々にして、ハイテクに分類されるテクノロジーは、特定の用途における効果を検証し評価が定まった後で一般向けに導入されます。これは、たとえば新型コロナウイルス感染症のmRNAワクチンなど、生命に関わる場合には妥当な進め方でしょう。しかしながら、AIのように直接的には生命に関わらない場合、方向付けが定まっていない初期段階における議論に多様な人々が参加することにより、個別には小さな力であっても影響を与えることが重要です。たとえば、ChatGPTのようなサービスにより生成された回答が、特定の障害のある人を差別するようなものであった場合、サービス上に用意された仕組みを介してフィードバックを返したり、SNSなどのメディアで話題にしたりすることで、バイアスを補正するよう促すことができるのです。
このように見ていくと、いっけん決定論的で不可避な変化をもたらすように思えるテクノロジーは実際のところ自在に解釈可能であり、初期段階における議論に多様な人々が参加することで方向付けることは可能であると私には思われます。次の節では、3名の方に監修していただいた事例を順に紹介しつつ、この立場から見つけた可能性や課題について共有します。
まず、「表現に寄りそう存在としてのAI」です。徳井直生さん(株式会社Qosmo代表/慶應義塾大学准教授・当時)が監修したこちらでは、画像生成AIを用いた連続ワークショップに取り組みました。参加したのは、メンバー11名、スタッフ6名です。会場内では、画像生成AIで生成した画像をモチーフとして制作中の作品の一部分や、ワークショップの記録などを展示しました。2021年以降、DALL·E、Midjourney、Stable Diffusionなど、テキストから画像を生成するAIが次々と登場して大きな話題となり、学習時にデータとして使用された作品を制作した人々の権利などをめぐって大きな混乱が起きています。このプロジェクトでの発見は、障害のあるアーティストとその制作をサポートするスタッフという二者の関係性が、AIが参加することにより「三角関係」へと変化し人間同士のコミュニケーションが促進されるということでした。ここから、単なる道具でも、人の代替でもない、「表現に寄りそう存在」としてAIを位置付けるのが適切であると私たちは考えました。これは、著書『創るためのAI』など、人間の創造性とAIの関係について探求し続けてきた徳井さんに監修していただいたからこそ見えてきたものであり、今後ますますAIの参加が増えると予想される私たちの社会を考える上で非常に重要な視点だと考えています。
次に、VR空間で演じるパフォーマンスの試み「CAST:かげのダンスとVR」です。緒方壽人さん(デザインエンジニア/Takramディレクター)が監修したこちらには、メンバー5名とスタッフ3名が参加し、ダンスはジャワ舞踊家の佐久間新さんがリードしました。佐久間さんは、これまでにたんぽぽの家と協働してきた中で、壁や机などの物と踊る、湯気のゆらぎを感じながら踊る、一人一人の即興的なやり取りを通して踊るなど、即興的なダンスに取り組んできました。緒方さんによるVRアプリ《CAST:かげのダンスとVR》は、光と影、陰の中の影を感じながら踊るダンス公演のリハーサルを緒方さんが見学した際に得た着想を基に制作されています。同じ物理空間にパフォーマーが集まり、VR空間で光源となってパフォーマンスするのです。会場内では、記録映像の上映にくわえて、HMDを装着して実際にアプリを体験できるようにしました。2021年秋にFacebookが社名をMetaに変更しメタバースに注力すると宣言して以降、VRに対する注目は大きく高まりました。すでにさまざまな試みがなされていますが、その多くは個別の物理空間からVR空間に参加するというものです。これに対して緒方さんが制作したのは、同じ物理空間にいる複数の人々が同一のVR空間に参加するという、世界的に見てもまだまだ例が少ないものです。会場内で上映した映像は、合計2回、1回あたり1時間半という限られた時間における試行を記録したものです。合計3時間という短い時間でも、VR空間の特性を把握したパフォーマー=メンバーたちがVR空間と物理空間を自在に往還しながら演じる様子からは、VRを超えたXR(Extended Reality)の新たな可能性を見出すことができました。これは、デザイン・イノベーション・ファームTakramで豊富な経験を持ち、同時にイヴァン・イリイチが説いた「コンヴィヴィアリティ」を足がかりとして現代に求められるテクノロジーのあり方を探求している緒方さんが監修されたからこそ見えてきたものだと思います。
最後に「実感する日常の言葉-触覚講談」です。渡邊淳司さん(NTTコミュニケーション科学基礎研究所 上席特別研究員)が監修したこちらは、福祉の現場において日常的に制作される日記、詩、ふと書かれる文章を題材に、講談師の神田山緑さんが講談として演じたものを、視覚と聴覚に触覚をくわえて体験するという試みです。会場内では、スタッフが選んだメンバー2名の絵日記と新聞を講談として演じた記録動画をみながら、神田さんが随所で釈台を張り扇で叩く際の振動を身体で感じることができるよう上映しました。一流の講談師による講談の記録動画を触覚とともに鑑賞するという体験は、それだけでも十分におもしろいものです。しかしながら、この段階では映画館で4DX版など「体感型」の映画を観るのと同様に、あくまで外部から観察するという関係性に留まります。これに対して、張り扇を手にして叩いてみることにより、外部からの観察者ではなく、神田さんが演じる日記の世界の中に入り、まさに現在の出来事として面白さをより深く味わうことができるようになるのです。これは、触覚とウェルビーイングについて研究し続けている渡邊さんが監修されたからこそ実現されたものです。触覚やウェルビーイングといったキーワードに興味のある方や、インタラクティビティ全般に興味のある方が体験すると、極めて重要な示唆を得られたことでしょう。
今回の展覧会に監修として関わっていただいた3名は、これまで表現とテクノロジーが交差する現場で継続的に制作し、議論を深めてきた方々です。本事業のような取り組みにおいては、その過程において何を行い、何を行わないかについてさまざまな判断や意見の対立があり得たはずです。実際のところ、今回の取り組みにおいてはそうした議論をする事はなく、阿吽の呼吸のようなかたちで進めてきました。ここで、暗黙の前提となっていたと思われることに少し光を当ててみましょう。展覧会初日に開催したシンポジウムでの発言を振り返ると、共通して「未来」ではなく「現在」について考えてきたことが分かります。テクノロジーについて語る際「未来はこうなるでしょう」という予想を提示することは、肯定的、否定的、いずれの場合にもなされます。肯定的な場合には理想郷として語られ、否定的な場合には暗黒世界として語られるわけです。これら2つの立場は大きく異なるように見えながら、現在ではなく未来について語っているという点においては同じなのです。
未来ではなく現在について考えることはなぜ重要なのでしょうか。この問題について考えるにあたり、韓国のSF作家で補聴器ユーザーのキム・チョヨプと、俳優・弁護士で車椅子ユーザーのキム・ウォニョンの共著『サイボーグになる——テクノロジーと障害、わたしたちの不完全さについて』を参照してみましょう。この本の第3章「障害とテクノロジー、約束と現実のはざま」においてキム・チョヨプは、難病や障害を抱える人に対する「いつか……」で始まる慰めの言葉について論じています。この言葉は、将来的にテクノロジーが発展すれば治療できるようになるだろうという希望を提示しようと発せられるものであり、往々にして「やさしい」テクノロジーだとして喧伝されます。しかしながらこれは、非障害者視点によるエイブリズムを前提とするものであり、現在の不完全なテクノロジーで不完全な身体をどうすればいいかを示してくれるものではありません。
先に紹介した3つの事例で扱ってきたテクノロジーは、いずれも未来のものではなく現在の——あるいはAIなど変化の早い分野においてはたとえ数日でも過去の——ものです。現在の社会に大きな影響を与えつつある段階で不完全だからこそ、そのテクノロジーの解釈は誰に対しても開かれており、今後を方向付けることができるのです。また、単に可能性を言葉で語るだけであればいくらでも誤魔化すことが可能です。これに対して、実際に体験した人々による記録を提示する、あるいは実際に体験できる作品として提示すると、人々が自分の身体で体験しその体験に基づいて批評できるようになります。まさにこの文章がそうであるように、話し言葉や書き言葉による言語は人間のコミュニケーションにおける主要な手段の1つではあります。しかしながら、話し言葉や書き言葉以外にも手話、文字盤、ジェスチャーなどコミュニケーションの手段は多数あり、手段ごとに手続きは大きく異なります。本事業に取り組んだ監修者たちの間で共通していた考え方とは、未来ではなくあくまで現在のテクノロジーに立脚しつつ、技術者や研究者も表現することで言語に限定せずコミュニケーションすることを重視していたことだといえるのではないでしょうか。
本事業からの学びを基に、まず信頼関係の醸成と表現活動の蓄積の大切さを振り返ります。その上で、新しいテクノロジーに関する議論を開き、次の段階へと進めていくことについての展望を述べます。
まず、メンバーとスタッフの間に十分な信頼関係が醸成されており、表現活動が蓄積されていることが重要です。十分な信頼関係があれば、仮に新しく出会ったテクノロジーに対して大きな脅威を感じた場合でも、メンバーとスタッフの間で共有し、受け止めることができます。これにより、リスクが想定される場合でも積極的に取り組めるようになります。くわえて、表現活動の蓄積があると、これまで行ってきた表現との違いをよく認識でき、新しい表現に取り組むための準備ができている状態になります。これは、メンバーやスタッフだけでなく、技術者や研究者にとっても新しい知見をもたらすことにつながります。たとえば、今回参加したアートセンターHANAのメンバーは、パフォーミングアーツの1つとしてダンスや演劇に取り組んできました。その中で、壁や机などの物と踊るなど、ダンスの中でもかなり挑戦的な課題に取り組んだことのある人々でした。そうした人々だったからこそ、通常の物理空間とは大きく勝手の違うVR空間においても、ごく限られた時間の中でその特性を把握することができました。さらに、そこでの体験を踏まえて出てきた議論からは、これまでのVRではあまり議論されていないような可能性を見つけることができました。この事例からは、同じ物理空間にいる複数の人が自在にVR空間に出入りするというアイデアが生まれました。これは、XRの考え方に基づいたもので、マルチプレイヤー型コンテンツの可能性を探求する先端的な研究・制作の現場からも注目され得るものです。短期間の取り組みから、具体的なマルチプレイヤー型コンテンツの例が生まれたことは、非常に価値があると言えます。
もう1つ大切にすべき点は、メンバーの自発性を失わないように待つということです。たとえば、今回参加した兵庫県神戸市の福祉施設「片山工房」メンバーの深田隆さんは、意志を表示する際に文字盤を用います。文字盤によるコミュニケーションの手続きは、口頭で話す、あるいはキーボードでタイピングするのと比較すると時間がかかります。深田さんを担当するスタッフの一人である榎宣雅さんは、文字盤による深田さんの発言が終わるまで必ず待ち、発言が終わった後、ひらがなで示されたものを漢字かな交じり文に変換していく際にも逐一確認をとっていました。これにより、障害のある人が、たとえコミュニケーションの手続きが異なる場合であっても、自発性を失うことなく表現につながる活動に取り組むことができるようになるのです。限られたリソースで取り組む活動において、正直にいえばこれは容易なことではありません。障害のある人々がこの活動に取り組める機会が限られており、遠方から参加する技術者や研究者が関われる時間も限られていたことから、ともすると拙速に結果を求めたくなる誘惑に駆られる事は何度もありました。しかしながら、表現活動に取り組む人々から表現につながる何かが生まれてくるまで待つということは、コミュニケーションのプロトコルにおいてもっとも重要なことの1つだったと今振り返れば思えます。
くわえて、人同士のコミュニケーションを十分に確保することも大切です。1月と2月に行ったワークショップで用いた画像生成モデル「Stable Diffusion」が当時受け取れるのは英語のみでした。今回の取り組みに参加した人々はすべて日本語話者でしたので、日本語から英語へと翻訳する必要があり、多くの人がDeepLなどの機械翻訳を用いていました。この状況は、本来なら日本語でそのまま入力したいのに、テクノロジーの制約により英語で入力しなければならず、不便だと思われるかもしれません。しかしながら、このようになっていたことにより、メンバーとスタッフの間で、どういう表現にすれば適切な英語になるのかに関するやりとりが頻繁に発生しました。また片山工房で参加されたメンバー、凪裕之さんの場合には、大学において英語を学んだ経験を基に、どの言葉を使うのが適切なのかということに関して、ご自身の意見を積極的に発言する場面が繰り返し見られました。これは私自身にとっても想定を超える出来事でした。もちろん、日本語から英語への翻訳を自動化してしまうことは容易です。機械翻訳サービスが提供する仕組みを間に入れることにより、人間には日本語しか見えず、画像生成モデルに対しては英語が与えらるようにすることは可能です。しかしながら、そうしてしまうことにより、メンバーやスタッフの関わり方や意識の持ち方はまた違うものになるでしょうし、英語での表現を吟味する機会を奪うことにもなってしまうでしょう。
表現という活動は現在を味わうことで、ときに強いストレスが伴うこともあります。しかし、スタッフと協力して乗り越えることで、新たな表現や制作意欲が生まれることにもつながります。「表現に寄りそう存在としてのAI」では、画像生成モデルを用いて誰でも気軽に表現できるという方向ではなく、これまでに扱ったことのないモチーフを自ら生成した上で扱うという点において、難易度を上げる方向に向かいました。たとえば、画像生成モデルが生成した画像をモチーフとして作品を制作中の十亀史子さんの場合です。2006年よりアートセンターHANAで活動する十亀さんは、これまでは写真集やイラスト集などをモチーフとして用いてきました。これに対して画像生成モデルが生成した画像は、如何様にも解釈できる曖昧な境界線が多数含まれるものでした。このため、これまでに用いていたモチーフと比較すると、より難易度の高いものとなり、それは制作においても強いストレスとなったそうです。しかしながら、そのストレスをスタッフと話しながら乗り越えられたことにより、これまでとは異なる表現へと発展させることができ、さらに制作を継続しようという意欲を高めることにもつながりました。例え辛いときがあっても、現在を味わうことができるからこそ、明日を生きようとする力が生まれ、結果的にウェルビーイングにつながるのではないでしょうか。
最後に、今回の取り組みから学んだ重要な点は、活動に関わるすべての人々のウェルビーイングが大切であるということです。この事業では、限られた期間で取り組むことが大変ではありましたが、得られた成果や学びが多く、関わった人々は生き生きとしていました。今回の取り組みを通じて私自身が強く感じたのは、こうした活動がスタッフや外部の技術者や研究者など関わる人々のウェルビーイングに与える影響の大きさです。先述したように、今回用いたテクノロジーは未来のものではなく現在のものです。それらを用いて自分たちの考えを表現していく場面において、メンバー、スタッフ、外部の技術者や研究者などの間で、それぞれお互いに影響を与え合うことが起きていました。誰かが誰かのためにつくる、ケアをされる人々に対して一方的にケアをするだけでなく、通常はケアをされる人々だとされる人たちに、通常はケアをするはずの人たちが関わる中で、ケアをするはずだった人々が、逆に自分たちの楽しさを見つけることでケアされるという場面が何度となく観察されました。本事業では、限られた期間の中で展覧会直前まで粘って取り組み、その結果を展示しました。これは大変なことではありましたが、そこに関わった外部の技術者や研究者としても、これまでに取り組んだことがないことに取り組み、そこから学んだことも多かったと思います。また、現在の技術を用いながら、今後の技術を左右することになるような発見につながったこともありました。そうしたこともあり、関わった技術者や研究者は実に生き生きとしていました。勿論、障害のある人々の権利を尊重することは極めて重要ですし、そのためにどうすればいいかという議論は今後も継続し、実践していく必要があります。しかしながら、そうした取り組みに施設の外部から関わる人々のウェルビーイングもやはり重要で、それがないと本当に価値を生むような活動を継続する事は困難になってしまうでしょう。そうなったときに残るのは、補助金や助成金を目当てに、テンプレート化された活動を繰り返す人々だけになってしまうかもしれません。そうではなく、メンバー、スタッフ、異なる角度から関わる外部の技術者や研究者といった人々が、それぞれうまく関わり、その活動を継続し、発展させられるようにするためには、関わる人々それぞれのウェルビーイングを考えていく必要があるでしょう。このことにあらためて気づけたのは、3つのプロジェクトに全体監修という形で関わることができたからだと考えております。
映画『Winny』の中で、金子さんがWinnyを始めとするソフトウェアを作ってきたことを自分の表現活動だったと紹介する場面があります。表現とは、視覚芸術や上演芸術に限らず文化芸術活動全般を含むかなり幅広い概念であり、人間がよりよく生きていく上で非常に重要な活動の1つだと位置づけられます。そう思ってみると、表現とケアとテクノロジーのうち、表現とテクノロジーはまさに一体化したものだと見ることができます。また、ケアとテクノロジーも、医療等のことを考えてみれば、もとより大変密接な関係にあります。であれば、表現とケアとテクノロジーのこれからという取り組みは、何か異質なものをあえて交差させようというのでなく、もともと密接に関わっている3つをちょっと違った角度から眺めてみようという活動だったのではないかと思えてきます。
今回の事業からの学びとして、今後こうした活動を展開していく際に参考にできることがあるとすれば、上記のようなことかと思います。表現とケアとテクノロジーのこれからと題した今回の展覧会で取り組んできた事は、当然のことながら、ここで終わってしまうわけではなく、さまざまな形で展開していきたいと考えております。この取り組みに参加していただけるのをお待ちいたしております。(2023年5月9日)
■参考文献
・キム・チョヨプ、キム・ウォニョン『サイボーグになる——テクノロジーと障害、わたしたちの不完全さについて』牧野美加:訳(岩波書店、2022)
・マーク・クーケルバーク『技術哲学講義』直江清隆、久木田水生:監訳(丸善出版、2023)
・長谷敏司『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』(早川書房、2022)
・ピーター=ポール・フェルベーク『技術の道徳化——事物の道徳性を理解し設計する』鈴木俊洋:訳(法政大学出版局、2015)
・渡邊淳司、ドミニク・チェン:監修・編著、安藤英由樹、坂倉杏介、村田藍子:編著『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために——その思想、実践、技術』(ビー・エヌ・エヌ新社、2020)
・Lillywhite, Aspen, and Gregor Wolbring. “Coverage of Artificial Intelligence and Machine Learning within Academic Literature, Canadian Newspapers, and Twitter Tweets: The Case of Disabled People.” Societies 10, no. 1 (March 2020): 23. https://doi.org/10.3390/soc10010023.
小林茂
博士(メディアデザイン学)。情報科学芸術大学院大学[IAMAS]教授。著書に『Prototyping Lab第2版』、共著書に『アイデアスケッチ』、監訳書に『デザインと障害が出会うとき』など。人工知能などのテクノロジーは、中立の単なる道具でもなければ不可避で抗えない決定論的なものでもなく自在に解釈できるものであると捉え、多様な人々が手触り感を持って議論に参加できるような手法を探求している。岐阜県大垣市において隔年で開催しているメイカームーブメントの祭典「Ogaki Mini Maker Faire」では2014年より総合ディレクターを担当。

2026年01月26日
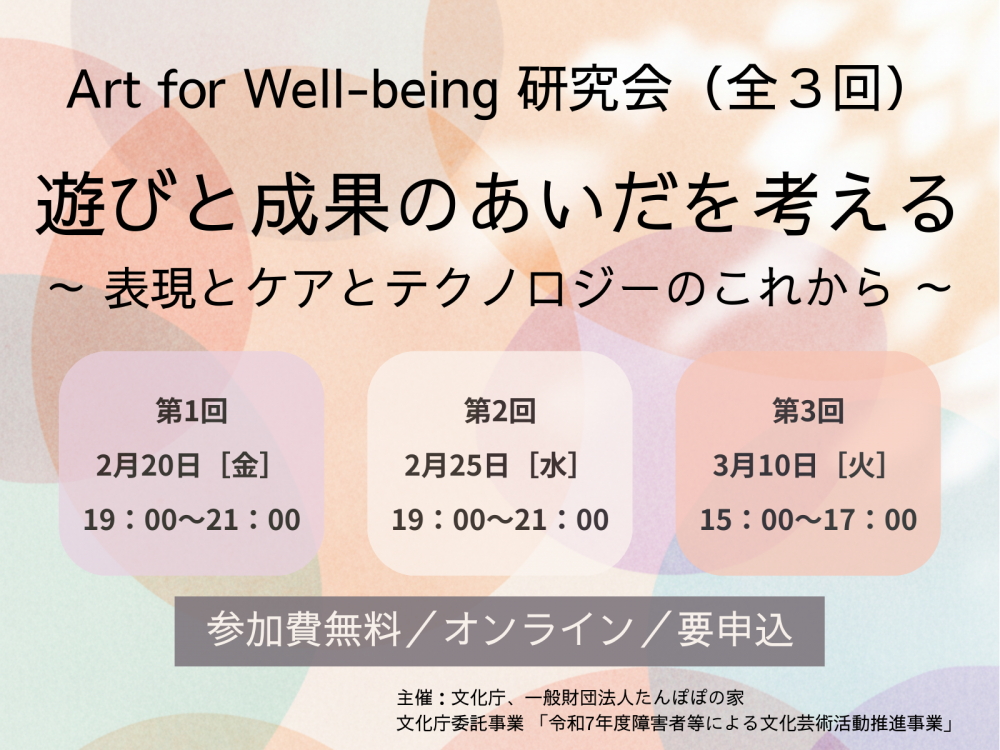
2026年01月26日

2026年01月26日



