2026年01月29日


目次
Art for Well-beingの取り組みの1つとして、2023年度にスタートした<とけていくテクノロジーの縁結び~ALSの体奏家、ジャワ舞踊家、踊る手しごと屋、インタラクション研究者のコレクティブ~>。チームメンバーは、進行性の難病ALSを発症した体奏家・新井英夫さん、たんぽぽの家のダンスプログラムもけん引されている、ジャワ舞踊家・佐久間新さん、踊る手しごと屋であり、新井さんのパートナーでもある板坂記代子さん、メディアアーティスト×インタラクション研究者・筧康明さんです。
今回レポートするのは、2024年6月29日にFabCafe Kyotoにて行われた、上映会&トーク「ダンス×ケア×テクノロジーの可能性を探る」の様子です。
トーク内容に感銘を受けたFabCafe Kyotoのスタッフさんが、この日の最終夜行バスに乗って、東京で開催されていた新井英夫さんの展示(終了間際)を見に行ったという逸話も残るほど、白熱したトークになりました!
*プロジェクトの経緯
2022年度
・2023年1月24日、2月14日 分身ロボットOriHimeを介してのダンス[レポート]
2023年度
・2023年11月23日 第1回ワークショップ。初めてリアルで一緒に踊る[レポート]
・2024年2月8日 テクニカルリハーサル。公開実験に向けて、実験1週間前に同じ会場で実施。佐久間さんはzoomで参加[レポート]
・2024年2月15日 公開実験[レポート]
2024年度
・2024年5月10日 ふりかえりオンライントークセッション。2023年度の活動をふりかえりました[レポート]
・2024年6月29日 上映会&トーク「ダンス×ケア×テクノロジーの可能性を探る」← 今回レポートします!
・2024年7月19日 公開実験に向けてのワークショップ
・2025年1月12日 テクニカルリハーサル(予定)
・2025年1月18日 公開実験(予定)
■日時 2024年6月29日(土)17:00-20:15 (受付16:30-)
■場所 FabCafe Kyoto アクセス
■参加費 1,500円(ワンドリンク付)
■参加人数 20名
■主催 文化庁/一般財団法人たんぽぽの家
文化庁委託事業 「令和6年度障害者等による文化芸術活動推進事業」
■協力 FabCafe Kyoto
■登壇者
新井英夫(体奏家/ダンスアーティスト)
自然に沿い「力を抜く」身体メソッド「野口体操」を創始者野口三千三氏に学び、深い影響を受ける。演劇活動を経て1997年よりダンスへ。国内外での舞台活動と共に、日本各地の小中学校・公共ホール・福祉施設等で「ほぐす・つながる・つくる」からだのワークショップを展開。2022年夏にALS(筋萎縮性側索硬化症)の診断を受ける。以降、対処療法を続けながら、車いすを操り、日々即興ダンスをし、各地でのワークショップ活動をSNSで発信している。
板坂記代子(踊る手仕事屋/身体と造形の表現家)
1979年山形県生まれ。大学で絵画を学び、絵本と版画の制作を行ったのち、2006年新井英夫の野口体操と体奏に出会い、即興をベースにした身体表現を学ぶ。2010年より新井とともに舞台公演活動および、身体と造形のワークショップを実施中。自身の活動として、「てきとう手しごと工房」主宰。糸つむぎなど原初的な行為を「感覚遊び」としてとらえなおし、暮らしに忍び込ませる探求をしている。
佐久間新(ジャワ舞踊家)
幼少の頃、臨床心理学者の父が自閉症児と研究室で転がり回っている姿を眺める。大阪大学文学部でガムランと出会いのめり込んで活動する。その後、インドネシア芸術大学へ留学。帰国後、日本のガムラングループと活動する一方、様々なダンサーとのコラボレーションを開始。たんぽぽの家の障害者との出会い以降、即興ダンスとマイノリティの人たちとのダンスに傾注。伝統舞踊におけるからだのありようを探求する中から「コラボ・即興・コミュニケーション」に関わるプロジェクトを展開。
https://shinsakuma.jimdofree.com/profile-1/
筧康明(インタラクティブメディア研究者/アーティスト/東京大学情報学環教授)
1979年京都生まれ。博士(学際情報学)。2007年に東京大学大学院にて博士号取得後、慶應義塾大学、MITメディアラボ等での活動を経て、現在は東京大学大学院情報学環教授を務める。物理素材の特性や質感を起点に五感を通じて体感・操作できるフィジカルインタフェース研究や作品制作、インタラクションデザインに取り組む。その成果は、CHI、UIST等の国際会議、Ars Electronica、文化庁メディア芸術祭等のアートフェスティバルや展覧会など分野を超えて発表され、受賞も多数。主な共著に「触楽入門」(朝日出版社、2016年)、「デジタルファブリケーションとメディア」(コロナ社、2024年)。
https://xlab.iii.u-tokyo.ac.jp
小林茂(博士[メディアデザイン学]・情報科学芸術大学院大学[IAMAS]教授)
オープンソースハードウェアやデジタルファブリケーションを活用し、多様なスキル、視点、経験を持つ人々が協働でイノベーションに挑戦するための手法や、その過程で生まれる知的財産を扱うのに適切なルールを探求。著書に『Prototyping Lab第2版』『アイデアスケッチ』など。岐阜県大垣市において2010年より隔年で開催しているメイカームーブメントの祭典「Ogaki Mini Maker Faire」では総合ディレクターを担当。
一般財団法人たんぽぽの家 Art for Well-being事務局
・小林大祐(トーク司会進行)
・後安美紀(トーク登壇)
昨年度は、2回の非公開セッションを行ったのち、限られたお客様をお招きして、限定公開実験ワークショップ公演を行いました。これらの一連の流れをまとめたダイジェスト版の映像はすでにYouTubeで公開しています。
今年度、新たに、公演フルバージョンとリハーサル未公開部分を含めた約70分の映像作品を制作しました(映像ディレクション・撮影・編集は丸尾隆一さんです)。本イベントはその初上映とそれを記念するトークイベントとして企画したものです。
予告編はこちら
20名の参加者に加え、FabCafe Kyotoのスタッフの方々も熱心にみてくださいました。



上映会とトークイベントの合間に見ていただくために、Art for Well-beingの取り組みを紹介するパネル展示も行いました。
トークイベントの司会進行は、たんぽぽの家・事務局の小林大祐が行いました。
まずは会場の皆さんから映像をご覧いただいた感想や考えたこと、質問などをお聞きしたいということをお伝えしたら、ありがたいことにたくさん手が挙がりました。
さっそく一番最初に手を挙げてくださった方は、なんと、昨年度同じくFabCafé Kyotoで行ったArt for Well-being京都報告展[ご案内][レポート ←京都報告展のレポートはpp.28-29にあります]にもお越しいただいたとのこと。その際、緒方壽人さん×佐久間さんとたんぽぽの家ひるのダンスで取り組んだVRを被ったダンス映像(CAST:かげのダンスとVR)もご覧になったそうで、それからさらにアップデートされているのか、その違いというものを感じながら今回の映像を見ていたとのことでした。
その方のコメント内容を以下にまとめました。
コメント1
●前半の本番の映像とセットで、後半のリハの試行錯誤の様子を見られたのが大変興味深かった。パフォーマーの試行錯誤に加えて、そこにテクノロジーを介入させていくときの筧さんの葛藤も見られたのがとてもよかった。
●自分自身も、会社で組み込み型のデバイスを使ってインタラクションをつくること等をしているが、このときに自分がどう動いたらいいのか、とても難しいと思っている。
●今回、福祉という場において、何か不自由を解決するというよりも、場をどう後押しできるのかというところに注力されていると思って見ていた。
●筧さんへ質問がある。できたものに対して突然方向性が変わってしまったり、技術的にみたらうまくいっていないのだが、それを受け入れられて話がどんどん展開されていくというときに、つくっている側としては、どういう気持ちで、どういう態度でいればいいのか。

それに対する筧さんの応答は、次のようなものでした。
筧
●支えるとか補助するというのは、最初の顔合わせセッションの段階でもう諦めた。諦めたというか、ここは補助するという話ではないと思った。ものすごいダイナミズムの中で関係ができているので、むしろどうやって入っていくか、どう関係を持つかということを常に考えていた。
●レインスティックが出てきた経緯も、打合せのときに、あずきのようにざざ~っと音がするものが欲しいという新井さんの発言を受けて、用意した。その意味では、後追い的な発想のようにもみえるが、やはりそれが出てきたことによって、次にまた体の動きが生まれてきて、途中で分解して壊してしまってというような、むしろそこはそうなってほしいと思う流れが結果的に生まれた。
●ただ、今回に関しては、じゅうぶんなフィニッシュを決めることもなく、というか、決めさせてもらえず(笑)。最後の最後で何が起きても関係していこうということで、流れの中でず~っと最後まで、あの場にいるということが目的だった。何かこっちの方向にいってほしいということもなく、こうしたらどうなるんだろうということを最後まで行った結果、ああいう感じになった。
筧さんのコメントは、ふつうなかなかないかたちで、粘り強くこのプロジェクトに関わっていることが伝わる内容だったと思います。
全体監修者としてずっと粘り強く関わってくださっている小林茂さんも、後から幾らでも説明はできるが、その渦中にあるときは、もうこの先どうなるかも全くわからない状態、つまり、この「とけていくテクノロジーの縁結び」のプロセス全体が即興だったとおっしゃっています。
会場では、別の方からも手が挙がり、次のような感想と質問を伝えてくれました。
コメント2
●映像の中で度々体を技術に例えているところが多かったように思う。例えば膝を立つときに膝をロックしてくださいとか、自分の意図をアンプリファイしてくれるみたいに感じる、とか。
●自分としては、そのことは、技術が身体になじむというより、身体が技術になじんでいくみたいに思えて、面白かった。
●みなさんにとってそれは、このワークショップの枠組みがテクノロジーだったから起こったコミュニケーションなのか、それとも、もともとよく使われる用語法、言葉なのか。
その質問に対して、パフォーマーの新井さん、板坂さん、佐久間さんは次のように答えました。
新井
●テクノロジーを意識してそういう言葉を使ったわけではない。
●アンプリファイするとか、ブロックするとか、ロックするとか、技術的な言葉のように思えるが、人間が作り出したほとんどの道具は、人間の機能を拡張しているものだと思う。
●例えば爪でひっかいて、モノが切れなかったり割れなかったりするから、ナイフをつくるとか、何か身体の延長上にシームレスに道具や技術やってきて、発展してきたのではないか。
●究極には脳の延長にコンピューターができて、人間が妄想したりイメージしたりする力がVRであるとか。身体のことを言語化していくと、そこら辺の言葉が重なっていくように思う。
●また動きということで言うと、僕は筋力がなくなっているので、重力とどうやって関係するかというのがよりシビアな問題。例えば体が傾いたときに力で頑張って立ち続けるのではなく、崩れていってちょうどいいところに骨を重ねる。これを鉛直線に骨を重ねるとか、重力軸に骨を重ねるみたいな言い方をすると、物理的でテクノロジーっぽく聞こえるかもしれない。でも、例えば建築だって柱を鉛直軸に重ねるというふうに表現する。地球上で起こっているものの動きや存在のあり方を言語化していくと、当然重なってくるのだと思う。
●少なくとも僕の中では境目があまりない。
板坂
●からだが技術に寄った、技術がからだに寄った、どうなんでしょうね。
●人が立つというのも、そこに何か技術があるわけで、技術がないと立てないわけなので、それは同時に起きているように思う。
佐久間
●踊りをやっていて、その踊りを自分でどうするか、あるいは誰かに伝えるかというときに、いろいろなことを総動員する。数学を使ったり、物理を使ったり、比喩表現を使ったり。
●結構今回のやりとりの中で、新井さんも僕も使った言葉にはベクトルという言葉があった。方向と強さみたいなのは、舞台上で一緒に動くときに自分が大事にしていることを共有しやすいと思って、使う言葉だったように思う
会場からは、さらに手が挙がります。
コメント3
●ダンスとテクノロジーとケアというテーマの中で、ダンスとテクノロジーは自分でもイメージができるが、ケアの定義というのがわからない。映像のなかで、確か、理学療法士さんも公開実験の場に来られていたということだったが、どんなコメントを発せられのか。
この質問に対しては、「僕でいいかな?」と新井さんが手を挙げて発言されました。
新井
●公開実験のときに、実は僕のALSの主治医の先生と、理学療法ではなく作業療法士の方が見に来られて、自分たちのやっていることと「すごく遠くないことなんだ」というようなことをおっしゃっていた記憶がある。
●理学療法(physical therapy)と作業療法(occupational therapy)の2つの専門領域があるが、理学療法は関節の動きを保つためなど、フィジカルな運動訓練を行うようなことが多い。一方、作業療法の「作業」というとどこか朦朧としている。実際、occupationalという英語を日本語に訳すときに難しかったらしく、作業という言葉は、ピタッと来ていなくて、うまく訳せていないらしい。
●本来その人が何かやりたいと思うような行動をサポートしていく、全般的にサポートしていくというのが、すごく本来的な意味での作業療法だと聞いている。
●映像の中でも言っていることだが、筧さんの装置で動きがレインスティックの音に変換されると、僕はそういう動きをしたくなって遊びたくなる。ついついやっちゃうみたいな状況をつくるというのは、簡単に言うと僕が遊びたくなっちゃうわけで、そういうモチベーションをつくっていくことは、生きるモチベーションを支えていく医療行為やケアとすごく重なっていると思う。
●テクノロジーのアイデアでそこの部分を助けてもらうという意味で、今回僕の中では、テクノロジーとアートとケアというのはぐるっと一つのつながりになる体験だったように思う。
この新井さんの発言を受けて、筧さんは次のようにおっしゃいました。
筧
●新井さんに向けたケアという話だけじゃなかった。僕もケアされた。
●流れの中でテクノロジーを通して関わっていくのは、すごく不自由なことだった。すごく時間もかかるし、壊れる時もあるし、思うように使われないし。
●ただ、その中で、もっとこうしたくなるみたいなことであったり、自分のつくったことに対してその可能性を引き出してくれるという感覚を僕は得ることができた。テクノロジーというものが常にケアの外側にあるのではなくて、その中に入ってお互いに関係し合うということがすごく体感できた。その意味で、僕はケアされたと思っている。
この筧さんの発言のなかにある、ケアの外側にあるテクノロジーと、ケアの中に入ってお互いに関係しあうテクノロジーという言葉に、わたし(=レポート作成者の後安)ははっとさせられました。ついついケアv.s.テクノロジーというような二項対立的な関係性を念頭においてしまいがちだったんですが、そうではない、少なくとも2種類の関係の仕方があるという気づきを得ることができました。
会場のみなさんとやりとりをしたあとで、登壇者が、ひとりひとり、映像を見た感想を述べました。以下はその内容をダイジェストでお伝えします。
「どうなるかわからない、何々しつつあるという、その只中にずっといる」と語る小林茂さん
ここにいる皆さんはおそらく事前情報はほぼないなかたでご覧いただいたと思うので、一体どういうことが起きるかわからなくて、次にどうなるんだろうと思って見ていたのではないかと思う。
渦中にいた私たちも、それと同じ状態で現場にいた。
これは極めて重要なことじゃないかと思っている。
というのも、私たちが時間について考えるとき、過去、現在、未来という言い方をして、現在というとずっと流れていくという捉え方をしているように思う。そうした場合、たとえ未来のことだとしても、どうなるかわかっていることというのは、完結してしまっているといえる。例えば、リハーサルを繰り返して、それが本番でも起こるということがわかっているんだったら、未来のことだったとしても、そこで完結していると。
それに対して、今回の場合は、どうなるかわからない、本当に何々しつつあるという、その只中にずっといるという状態が続いていたというふうに思っている。そういう意味で、映像を通してそのことを感じた皆さんと、物理的にリアルタイムでそのことを感じたわれわれも、どうなるかわからないという只中にいた経験を共有できているという状態から、今日はいろいろお話ができるのかなと思う。

「今回はみんなに何が起こっても何とかする力があった」と語る新井さん
タイトルに即興というキーワードは入っていないが、即興性が高かったと思う。即興って何だろうという話をかつて看護系の先生と話したことがある。心のケアの現場で即興的なことがすごく大事であると。決めたことをそのままやっても追いつかないから、その場そのことをその人が何とかする力というスタンスでやっていると。それがいいなと思っている。
今回はみんなに何が起こっても何とかする力があった。それはある方向があって、絶対こうするという、ねじ伏せるような力ではないが、例えば誰かが困っているとか、予想外のことが起こり、何か今違う流れだなと思ったら、それを受けとめて、みんながそれを前に運んでいくようなことをやっていた気がする。
だからやっていて、実は実験中の公開実験のときも、安心感と、おもしろいなという気持ちがずっと続いていたのを覚えている。こんなことをしているのに余計なことしやがってとか、そういう感じではなかった。
特に公開実験のとき、筧さんの用意されていたあるデバイスが思った通りに動かなかったのだが、そのことも含めて、いや、この場はこの場で何かやりましょうという、気持ちがあった。困った覚えがない。
でも、これって何なんだろうと思う。あんまりそういう場はないんじゃないか。
「少なくとも僕の視点からはすごく贅沢な体験をさせてもらった」と筧さん
みなさん、本番の映像を見て、そんなにテクノロジーが関わっていないぞと思ったのではないか。それは、本番直前にレインスティックが全く動かなくちゃったから笑。僕の人生の中で一番全く動かなかった。
公演中、僕はぼーっと、ただただ「はあ~~~」という喪失感の中で見ていた。
今日初めてちゃんとこの公演を映像を通して見ることができた。
でもそこで立ち上がってくる皆さんの想像力の中でできてきたパフォーマンスを見て、今本当にケアされている感じがする。本当に本当にこんなんでいいのかと思いながら。ただ、そこはすごく贅沢な体験だったなと思っている。
何かを支えるとかという、補助するというタイプじゃなくて、テクノロジーも等価のように関わっているというときに、やはりそこには不具合もあるだろうし、うまくいかないこと、あるいは想定しない可能性というのはどう引き出されていくということがある。
「筧さん、これをつくっておいて」「これをどうにかして」ということは一切なく、それぞれの中でコレスポンダンス(万物照応)というか、応答し合うことによってできてきたもの、そしてそれがドラスティックに本番で壊れるということも含めて、振れ幅があったことは、少なくとも僕の視点からはすごく贅沢な体験をさせてもらった。
「自分だけが感じている彼の重さを、遊びながらみんなとも共有できたことは大きい」と語る板坂さん
私は普段は新井英夫のケアをするという立場でいる。家族としてプライベートで生活を共にしているので。
普段、人の身体を立たせるとか、座らせるというときに、自分だけが味わっている、彼の重さみたいなものがある。時々辛くなるというか、私だけが支えているという、辛くなる重さもある。でも同時に非常に豊かな重さと向き合っている、ゆたかな時間でもある。
単純に介護だけではなく、身体的な遊びとしての重さ。それを一人でやっている。
それが今回こういった実験の場所で、佐久間さんや筧さんやたんぽぽの家の皆さんと遊びながら共有できたというのは、すごく私にとっては大きい。
立つ、歩く、寝転ぶ。その中で新井さんもできる、手を上げるという表現。そういったことを一つ一つ丁寧に追えたというのが、私の中ですごく安心感があった。踊って何かを表現しなくちゃいけないのではなくて、人間の動作の一つ一つを丁寧に見ていくということが本当にありがたかった
また、本番は動かなくなったとは言え、見える形でテクノロジーと一緒に存在しているというのが、今回私は面白かったなと思う。
私も全体を見たのは今日の上映会が初めてだった。音と動きの世界だったなと思った。動きのあるところに音があり、音のあるところに動きがある。単純な話なんだけれども、改めてそれを感じた。
「テクノロジーをかませれば、少しは何かわかりやすく見えるのではないだろうかという期待があった」と語る佐久間さん
いろいろ渦巻いていて、どれから話そうかわからなくなってしまうんですけれども、いくつか感想を述べたい。
まずは、板坂さんが音の話をされたので、それに関連して。
ふつうは音楽があることが多いと思うが、われわれの試みには、音楽がなかった。だけど、板坂さんが特に音、いろいろと床をこすったり、最後のシーンで紙風船をポンポンポンと手のひらでバウンドさせるシーンがあった。その音がものすごいよかった。すごい音楽的というか、いい音が聞こえた。
紙風船はすごくコントロールしにくいと思う。サーキュレーターの上でぽんぽんぽんどれぐらいのタイミングで出てくるかどうか、もう一回バウンドさせようと思うと、また次がどれぐらいのタイミングで落ちてくるのかというのが、楽器として考えるならかなり難しい演奏になると思う。そういうような中で、絶妙のタイミングで音が入っていて、それをやはり新井さんとか僕は音楽として聞いていて、それで動いていたような気がする。映像を見ていてもそういうふうに見えた。それがどれぐらい他の見ていた皆さんと共有できているかわからないが、そういう音の世界がよかった。
新井さんも僕も、割りとワークショップをたくさんしている方のダンサー/アーティストだと思うが、僕と比べれば新井さんの方がいろいろな装置を使ってはるかにわかりやすいワークショップをしているように思う。
わかりやすいというと、何かよくないことのように思われるかもしれないが、全くそうではなく、参加した人が「そういうことか!」と納得する、すごく説得力のあるワークショップをされている。
僕の方は、わかりにくいと言われることが多い。何かわかっているんだろうけれども、一体何が起こっているのかよくわからないとか言われるタイプのことをしている。それをどうにか、筧さんに関わってもらうことで、少しでもわかりやすいように、テクノロジーをかませれば、少しは何かわかりやすく見えるのではないだろうかと、そういう邪な期待をもって(会場爆笑)、筧さんにお声がけしたところがある。でも結局わかりやすいものになったのかどうかが気になるところです笑。
「映像は映像で出来事をよみがえらせる力がある」と語る、事務局・後安
小さなモニターを通して、字幕チェックするなど何度か映像は見返していたが、今回初めて大きな画面で落ち着いて最初から最後まで見させてもらった。それでやはり映像は映像で出来事をよみがえらせる力があるんだということを強く感じた。
要は映像だとよく見えるところがいっぱいある。本番で、私は端っこの方で見ていたので、仮面をつけて寝返りを打つところシーンは実は真っ黒で全然見えなかったが、映像は、光が当たっている方から撮られていて、しかもそのままでは暗いので、さらに明るさを補正して見えるようにしてくれた。それで、ああ、こうなっていたんだというのが、初めてわかった。
ただ一方で、窓を開けた瞬間に風が入ってきて、枯葉がカサカサと転がるような音が聞こえたときの感動というのは、現地にいないとわからないだろうとも思う。当たり前だが、映像と現場というのはそれぞれ違うものがあり、映像には映像独自の力があると思った。今回、丸尾隆一さんというすばらしい映像作家さんが関わってくれて、丸尾さんの力が大きいとは思う。
ひととおり登壇者が映像を見た感想を述べたあとで、フリーディスカッションが始まりました。
展示「影ダンスを一緒に」について
口火を切ったのは、東京都現代美術館(以下、現美)で「翻訳できない わたしの言葉」という展覧会[URL]を開催中の新井英夫さんでした。新井さんいわく、現美の展示を企画するにあたって、この「とけていくテクノロジーの縁結び」がとてもヒントになったそうです。
現美の展示会場には、これまで新井さんが行ってきたワークショップのアイデアが散りばめられていたのですが、その中の一つに、新井さんの手の影と一緒に影絵をつくる、「影ダンスを一緒に」というコーナーがありました。
2月の公演のときも、天井に寝転がって手で影を作ってというシーンがありましたが、全くそれと同じように、ご自宅で再現して、自分の手の動きを天井に映したものを撮影し、展示会場でプロジェクションしました。来場者に対しては、それを見て、自分の手の動きを重ねて自由に踊ってください、そしてよかったら、それを撮影し、SNSにその動画を上げてください、という指示書を掲載していました。
SNSに上げられた動画を見た新井さんは、自分で見ても自分の中に半分ぐらい、どっちが自分の影かわからなくなる瞬間があったり、もう同じ動き、自分ができないなと思うんだけれども、でもその過去の自分と今来た来場者の人が踊ってくれているというところに何が言葉ではできない安心感というか、幸福感が沸き上がったと言います。
自分の中に自分の身体がどんどん何かできなくなってくるんだけれども、それが記憶として残っている。非常にプリミティブなものかもしれないが、テクノロジーを通して確かにそこにある。それに対してまた誰かが関わってくれるということ自体の安心感、幸福感。
身体がそこになくても、何か自分と関係をつくってくれる人が未来にいるという喜び
それって何なんだろうと考えるとき、新井さんは、さきほど小林茂さんが言った、未来という時間のことを考えるそうです。
未来に対して、これからどうなるかわからない自分の身体の未来に対しての安心感。
自分の身体がそこになくても、何か自分と関係をつくってくれる人がいるという喜び。
まだこの感覚は、新井さんのなかでもつかみかねているそうなのですが、ひとつ言えることは、VR(バーチャルリアリティー)で自分の身体がアバターになって、何らかのテクノロジーで自分がVR空間で自由に動いていて、それが楽しいなというのとは、違う気がするということです。
かつての自分の姿がそのままある場所に記録として残り、でもそれが、今の時間とも未来ともちゃんとつながり続ける。不自由を不自由なまま遊べると、すごく楽しいことではないかと新井さんは言います。
今までやってきたことが何かやっと生きてくるという感じ
ここで、新井さんから直接バトンタッチされた佐久間さんは、次のように語ります。
今回でいうと、新井さんがALSにり患されているからこそのプロジェクトだと思うが、他にも、例えばコロナになったときに、オンラインを通してそれぞれの家の中にあるもので踊ってみようという試みをしたり、「ふつう」の状態だったら、ふつうに体使って踊ればいいじゃないかとなるところが、著しく制限されたなかでの試行錯誤を通じて、つながりを感じたり、あんなものでも踊れるんだというリアリティが生まれてきた経験を、自分たちは積み重ねている。
だから、我々が病気になったり、災害に遭ったりとか、体がどんどん年をとってきたりする中で、まだ踊れるとか、その状態でもどうやったら踊り続けることができるか考えていきたいし、今回のプロジェクトを通じて、今までやってきたことが何かやっと生きてくるように感じたと佐久間さんは言います。
遊びとしての関わり代が大事
新井さんと佐久間さんの話しを受け、筧さんが「いいですか」と自分から手を挙げました。
筧さんは、ご自身が受け持つ学部生の授業で、「いろいろな美術館に行って作品を見てきて、そこで一番気になったものを発表してください」という授業をしたそうなんですが、ある学生さんが、新井さんの現美の展示をみて、「影を重ねて遊べるすごい楽しい作品でした」と語ったそうです。
筧さんが言うに、背景のことももちろん理解していたんだけれど、まずそこの遊びとしての楽しさを彼はつかんで発表していたと。まず遊びとしてそこに関わり代をきっちりつくるのがとても大事なのではないかと筧さんは言います。
影はバーチャル。バーチャルというのは本質的にはリアル。影には本質的な強さがある。
さらに筧さんは続けます。
この日のディスカッションのなかには、遊びや実験という言葉が多々出てきましたが、筧さんは、VR(ヴァーチャルリアリティ)とは本質的にリアルであるということだと、バーチャルという言葉にある、「本質的な、実質的な」という意味を強調しました。
少しだけ、わたし(=レポート作成者の後安)のほうで補足しますと、例えば、バーチャルリアリティといったとき、仮想現実と訳され、バーチャルはどうしても現実と対義的な関係にあるように思われがち。「バーチャル」の反対語は、「リアル(現実)」だと思う人も、もしかしたらいるかもしれない。でも、「バーチャル」の反対語は、「nominal(名目上の、名前だけの)」という言葉だそうです。少し古い例ですが、ビル・クリントン氏がアメリカの大統領だったとき、ビル・クリントン氏はnominalな大統領で、バーチャルにはヒラリー・クリントン氏が大統領だと皮肉交じりに言われていたとか。
筧さんは、影こそが、VR(バーチャルリアリティ)であり、遊びとして、本質的な強さがあると言います。
そして強度だけでなく、そこには、余白としての遊びもある。いわゆるアバターのようなものだと、こうしかしちゃいけませんという、どうしてもそこに固定的な関係が成立してしまう。それに対して、影には、他に遊べる余白があると。それがすごく重要なんだなと筧さんは強調します。
次はむしろ直すとか壊れるとかということも含んだ遊びを、テクノロジーの側面からつくりたい
そしてとうとう、ここで、今年何をやってみたいかというアイデアが筧さんの口から飛び出してきました!
余白があるということ。
筧さんにとっては、紙風船もしかり。人が積極的に関わるのもよし、まったくほったらかしでもよし。紙風船の常態として、何かしらの空気の流れに影響されてちょっと動いているという、関わり代に余白があることが大事だと言います。
筧
●直接的に関係を持つことと、全く関係を持たないこと。壊れてしまうというのはその究極の状態。その両極を昨年度の公演で体験できたのはよかったのだが、もっと欲を言えば、壊れてもまた直しながら遊び続けるようなものが、あの場でもしできたら、もっと豊かな体験ができたんじゃないか。
●そこで、今年は、むしろ直すとか壊れるとかということも含んだ遊びを、テクノロジーの側面からつくることができたらいいなと思っている。
筧さんから投げかけられた「直すとか壊れるとかということも含んだ遊び」のアイデアを受け、話がどんどん展開していきました。
新井
●電化製品が3年ぐらいで壊れるように時限装置込みで作ってあるという都市伝説があるが、それと同じようにパフォーマンスの最中に30分後には壊れると予告されているデバイスがあると、同じ時間を過ごしていたら、何か生きているうちに何かこいつと遊んであげようかと、妙に擬人化されたりして、いいような気がした。
●原発のように壊れたら困るという技術分野の動きもあると思うが、何かが壊れることを前提に、アートという領域だからこそ壊れることを前提にテクノロジーが関わってくれるというのは、お互いに許容範囲が広がっていいのではないか。
●体がそもそもそういうものだと僕は思っている。思い通りにならないし、病気になるし、3か月後どうなっているかわからないし。それを補うための屈強な技術があるのでなくて、技術も非常に危ういものだとか、壊れやすいものだという前提に立って、そこで何ができるかを考えるのは、我々がやっているプロジェクトだから許される、面白いところだと思う。
小林茂
●Art for Well-beingプロジェクトには、「表現とケアとテクノロジーのこれから」という副題がついているが、表現とケアとテクノロジーと、3つ並んでいることが秀逸だ。
●ケアとテクノロジーの2つだけだと、いろいろな問題をテクノロジーを使って支援するという、基本的には支援の話になる。そのモードにある限りは、動かない、途中で壊れるなどは、あり得ない話(例:医療機器)。
●しかし、そこに表現が加わることで、別の可能性が開けてくる。もちろん表現だから何かが壊れてもいいとか、そういう話では全く、表現は表現独自の厳しさはあると思うが、表現が入ることで、違うテクノロジーのあり方みたいなものが初めて見えてくるのではないか。
佐久間
●新井さんや板坂さんは野口体操を、僕はジャワ舞踊をベースにやっている。それぞれ違うベースなのだが、このメンバーだからうまくいったところもあると思う。
●ジャワ舞踊には、バリュミリ(水が流れるように)という教えがあり、ままならないものでも水のように融通無碍にいくことが大事だと思っている。
●何が起こっても受け入れる、あわせていく、そうでなければ舞踊的ではないというところで、これまでやってきた。
新井
●野口体操には、ジャワ舞踊と違って、特定の型はないが、佐久間さんが言ったような、水の流れのような動きとか、重力に無駄に抵抗しないで仲良く動く、というようなところを根本理論としている。
●僕は最後10年ぐらいご本人から直接習うことができたが、もともとこの体操を作った野口三千三(1914-1988)という人は優れた体操の教師で、兵士の訓練も行っていた。日本が戦争に負けた1945年、東京大空襲で死体の片付けや自分の教え子がどんどん亡くなるなどし、いわゆるPTSD的な状況になって、心と体のダメージを受け、腰痛になってしまった。
●医者からは治しようがないと言われた腰痛を、彼はどうしたかというと、無理に動かないという選択をし、体に負担を与えないように動こうとした。そうしたら、結局力を抜くとか、腰痛を抱えながら動く、重力に無駄に抵抗しない、という方向から野口体操の理論ができてきた。
●だから、外科手術のいい先生を見つけてきて、パーツを組み替えるなどして、不具合を治そうという発想ではなく、でこぼこを均質化することなく、不具合を抱えたまま、受け入れてなんとかしていこうというところは、佐久間さんとの共通点としてあった。
外側とずっとつながっているという楽さ
新井さんは、さらに話を続けます。
新井さんが言うには、野口体操には、型はないが、完全フリーでもなく、重力の方向に対してこういうふうに体を使った方がいいよとか、逆にこれをやると怪我するよとか、シビアなところもあるそうです。
そこが近代的な自我、私(ワタクシ)を表現するコンテンポラリーなアートとちょっと違うところだと、新井さんは考えておられます。
即興でいろいろなダンサーや音楽家とやってきて、うまくいかないときというのは、だいたい自我のぶつかり合いのようになってしまうとき。俺が、俺が、俺の表現がどうだ、うまいぞみたいな、そういうのがあると、面白くも何ともないと。
新井さんいわく、野口体操には、何か大元が、自分が伺い知ることのない、自分が意識化できる世界の外側から来ていると捉えるところがあるそうです。
外側とずっとつながっているということ。
内側を出し続けるというのは、辛くなってくる。
だから、相手からもらったエネルギーをちょっと自分が変えて外に出す。そして出したものをまた誰かが拾って違うものにして変えてくれる。今回は、それがあったので、すごく楽だったそうです。
何を「美しい」と感じるのか、美の価値観を新しく更新していく
このパートでは、パフォーマンス中に、佐久間さんの動きを物体として美しいと感じた板坂記代子さんの発言をきっかけに、「美」について議論が始まった様子をお届けします。
新井さんのパートナーとして、日常のケアの場でも新井さんに関わっている板坂さん。ある意味、この世のなかで一番身近に新井さんに接し、新井さんの動きや身体的な変化を感じてきた人であるといえます。
しかし、その板坂さんにしてみても、今回の公演で行った、棒(レインスティック)をつけて立つという行為は、生まれて初めての経験だったと言います。
レインスティックをつけて立った状態から、座っていくシーンがあり、その後、コミカルなシーンへと展開していくのですが、実は、公開実験の現場に駆けつけてくださった新井さんをよく知る人からも、あれは相当危なかったのではないか、と心配されたシーンでもありました。新井さんも、「やばかったよね、あれはね」と転倒しなかったことをオンライン越しにぼそっと寿いでおられました。
板坂さんは、そのシーンのことを次のように回想されました。
あの時、佐久間さんが後ろにすーっと来てくれて、片身で座っていったときに、すごく美しいなと思ったんです。物体として。じわーっと沈んでいく体重が。
そのままではからだにレインスティックが刺さってしまう。サーカスの綱渡り的な要領で、レインスティック1個を外したこと。抜き差しならない動きというのが面白かったなと思って、映像を見ていたと板坂さんは語ります。
佐久間さんも、ケアとダンスがどう関わっているのかという問いを続けます。
自分のダンスはわかりにくいと言われるが、ケアとダンスは、関わっていないはずはないし、いろいろな身体のことを思いやるとか、いろいろな立場の人を思いやるとか、そのことを考えながら動くということが、いいダンス、美しいダンスをつくっていくに違いないという確信がある。
それを聞いた、新井さんは、美しいという言葉を使うことへの迷いがあると、みなに語りかけます。

例えばクラシックバレエ的な美しさ、伝統的な磨かれた、これがこの美しさなんだみたいなところに向かおうとするときに、そこからは、そこに向かえない人、身体的条件に向かえないとか、文化的背景的に違うところにいる人は排除され、非常に限られた美になってしまうと思う。
一方で、障害福祉の現場でワークショップし続けられたのは、自分の中で想定外の美意識みたいなのが発見できたときがあるからだ、と言います。自分がこういうのが美しいと思って動いていたけど、この手があったかと。半ば嫉妬してしまうような、うわあ、いいなあと思う瞬間がたくさんあった。
つまり、新井さんが言うには、美というものを狭く捉えると優生思想的になり、とても危うい概念だが、美しいというものを発見し合いたい、新しく創っていきたいという気持ちがあるということでした。
ただ「今回の映像とか見ると、自分の想定していなかった美しいなあと思う瞬間がたくさんあった」と正直な思いも告白してくれた新井さんでした。
その話を受けた佐久間さんは、次のように語ります。
今、新井さんの口から何か嫉妬するみたいな言葉が出たので、敢えて自分も言うけれども、例えば映像の中で、影の時に鉛直に立てた新井さんの手の動きに、ああ新井さんのほうがいい動きだと、僕は嫉妬する。
仮面つけていろいろ体を動かしているときも新井さんは非常にいい動きになる。それは麻痺しているということが大きいのだが、ダンサーは困ったことに、そういうからだに憧れたりしてしまう。でも、ふつうはそれは簡単には言えない。
なぜなら新井さんは病気でどんどん進行していって動かなくなるのだから、そんな美しいとか言われてもと思うはずだから。
佐久間さんの告白のような言葉を受け、新井さんは、「あの、ね」と間をおいて、言葉をていねいに選びながらゆるりと語り始めました。
今、自分の領域が、自分でもわからなくて、ダンスをやっている、やってきた人間ですみたいに今はしゃべっているけれども、重度身体障害者の当事者でもあるし、ケアしている人から全面的にケアされないと生きていけない人間になった。
そこから見ると、お互いに納得ずくで、みんながこれ美しいねとか、面白いねっていうのはケアの現場にどんどん持ち込んでいい概念ではないかと思う。外から格付けされると、嫌な人もいるかもしれないけれども、そこはどんどん価値観を更新していっていいのではないか。少なくとも僕は、佐久間さんが気にしていたようなことはあまり意識しない。
登壇者どうしのフリーディスカッションを経て、気づけば、予定していた時間が残り10分間になってしまっていました。
進行の小林大祐が、ふたたび会場の参加者の皆さんに、「うまく言葉にならないこともあるかとは思いますが、ぜひ会場の皆さんと一緒に言葉にしていけたらうれしいです」と質問や感想の呼びかけをすると、「テクノロジーのサイドから見た即興とは何か」と「テクノロジーとしての仮面、全く違う形のVRとしての仮面」という、大変興味深い論点が掘り下げられました。
テクノロジーのサイドから見た即興とは何か
コメント4
●即興という言葉と身体という言葉、2つのキーワードが自分の中ですごく浮き上がっている。
●テクノロジーと福祉というとき、例えばセンサーを使ってセンシングをし、無線で飛ばして魔法のように動くというような、ともすれば、テクノロジーがニューメディアとして暴力性や権力性を帯びてしまうことが危惧される。
●けれども、今回、感動したのは、テクノロジーと福祉がフェアな関係にあるように見えたことだ。そのフェアな関係を生み出したのが身体性と即興性なのではないかと、話を聞きながら思った。
●ただ、テクノロジーは、センシングしてすぐに反応できないという、どうしてもタイムラグが発生してしまうところがある。
●小林茂さんと筧さんに、テクノロジーのサイドから見た即興というところを伺いたい。
筧
●即興的でありたいと、このプロジェクトに入る前からずっと思ってきた。いろいろなインターフェースの研究や作品をつくってきていて、完全にコントロールするということだけではなく、コントロールし得ない部分も含めて関係をし続けているメディアを、それをニューメディアと呼ぶかどうかは別として、作り続けたいという思いがあった。
●即興の即という、どれぐらい即応的に応答するのかということだが、パフォーマーの皆さんの応答の速度とテクノロジーが動作するときの速度、そしてそれをまた改変したり、つくるときの速度というのは全く違うタイムスケールを持っている。
●それを合わせに行こうとするとやはり無理がある。そうではなく、異なる時間軸のものがお互いに関わっているという状態をどうつくるかということがすごく重要だと思う。そのあいだに作り手として、エンジニアなのか、アーティストとして関わるのか。間に人が関わることによって、異なる時間軸の営みが関係し合うということ。それが今回ある部分でうまくいって、ある部分はうまくいかなかった。
●テクノロジーは人の手を離れることを前提とするというところはあるのかもしれないが、今回、あくまで人の手を添えながら、ずっとテクノロジーと寄り添いながら最後まで走ったといえる。むしろそういう、手放しすぎず、手元にありすぎない、という関係をこれからの技術というのは取り返す必要がある。技術とどう手を結ぶかというのが今回の学びであり、これからチャレンジしたいところでもある。
小林茂
●やはりテクノロジーというと、さきほどの新井さんの言葉を借りると、すべてをねじ伏せようという、自我のぶつかり合い的なテクノロジーばかりが主流になっていて、その結果、どうもいろいろなところに問題が起きてきているように思う。
●それに対してジャワ舞踊のいう、水が流れるようにとか、野口体操でいう重さを感じながら、それがある意味ままならないところでそれに沿っていくというのは全然違うものだと思う。
●全てを思ったとおりにしよう、コントロールしよう、決めたとおりに動く、それが100点満点でうまく動かなかったら減点法で引いていくみたいなものになると、未来のことなんて、新しいことはない、起きることが全部わかっていることになる。
●今回の試みはそうではない。何がどうなるのかわからない、本当にどうなるかわからない。その中にいる、みたいなときにおける即興というもののときに、不具合が起きたらすぐに直すという即興もあれば、何かがうまく動かなくなったことによって、また次のアクションが起きていくという、そういう全体を見ての即興というのもありえると思う。
●ジャワ舞踊的なテクノロジー、野口体操的なテクノロジーのやり方や即興の仕方というのは、どういうものだろうかという示唆を今回いただいたと思っている。
テクノロジーとしての仮面、全く違う形のVRとしての仮面
コメント5
●映像のなかで、仮面がすごくおもしろいと思って見ていた。それまで顔を出されてパフォーマンスをしていた。新井さんは重度の身体障害のあるなかで、動いていた。佐久間さんは踊れる人、踊りに対して身体的な経験がすごくあるような動きをしていた。
●それが仮面をつけた瞬間に「その人である」というのが一瞬わからなくなり、何か違った動きとして見ることができた。誰かと何かがそういう動きをしているという空間になっていたような気がした。
●その辺りの感想を伺いたい。
佐久間
●あの仮面は、ジャワ島のジョクジャカルタという町の仮面をつくる作家の人が、伝統的なものではなくて、新作としていろいろな仮面をつくっているのをたまたま私のパートナーがジャワで買ってきたもの。
●テクノロジーといえるのかどうかは分からないが、仮面は非常におもしろい道具である。さきほど言われたように、つけることによって、存在が変わってしまう。それも非常に微妙なもので、人によって似合う似合わないもあれば、同じ仮面を別の人がつけたら全然違って見えることもある。
新井
●仮面というのもテクノロジーだと思う。人間以外の動物は仮面はかぶらない。あれをかぶって何かになったつもりになるというのは、人間が発見したテクノロジーの一つだと思う。相当昔から、人間は結構な発明をしている。
●おもしろいのは、かぶっている本人は自分の姿は見えないが、かぶっているときは明らかに別モードに入ってしまう。自分でも仮面をつけたシーンは、あそこだけセリフを念入りにしゃべったりした。何かのキャラクターになったような気は確かにした。
●それがお客さんにも何かまた別のモードに見えたのだったら、とてもおもしろい。
筧
●いや、それもまた全く違う形のVRなんだなと思って聞いていました。
終了時刻を過ぎても、まだ話が尽きないということで、しばらく皆さん残ってあちこちで話し込んでいる姿が見られました。終わるのがとても名残惜しい上映会&トークセッションになりました。
冒頭でも申し上げましたが、トーク内容に感銘を受けたFabCafe Kyotoのスタッフさんが、この日の最終夜行バスに乗って、東京で開催されていた新井英夫さんの展示(終了間際)を見に行かれました。ここに載せた写真はすべてその方が撮影したものです。
写真提供:FabCafe Kyoto
構成・文:後安美紀
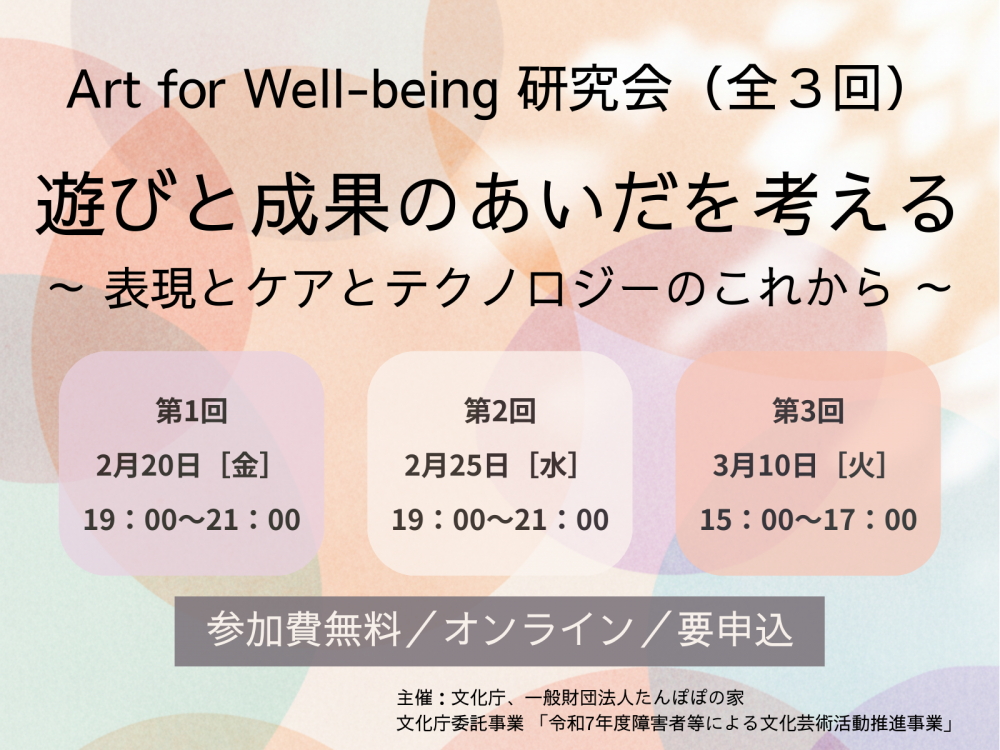
2026年01月29日

2026年01月26日





2026年02月04日